春から夏にかけて暑くなり、秋から冬になると少しずつ寒くなっていく。
そんな日本の四季が、最近ヘンだと思いませんか?
夏になると気温が40度を超えることもあり、熱中症で病院に運ばれる人がとても多くなります。
世界でも同じような異常気象が起こっていて、死者が出る事態となる地域もあります。
生命をもおびやかす異常気象。
しかしこの酷暑も、あと少しで終わるかもしれません。
2015年イギリスで開かれた王立天文学会で発表された、とても興味深い研究があります。
「2030年代に太陽の活動が60%低下し地球は小氷河期に入る」
というものです。
この記事では、この「小氷河期」について分かりやすく紹介しています。
- 小氷河期が来るという科学的な根拠
- 小氷河期が始まった場合に出てくる影響
2030年氷河期が来るという科学的な根拠とは?
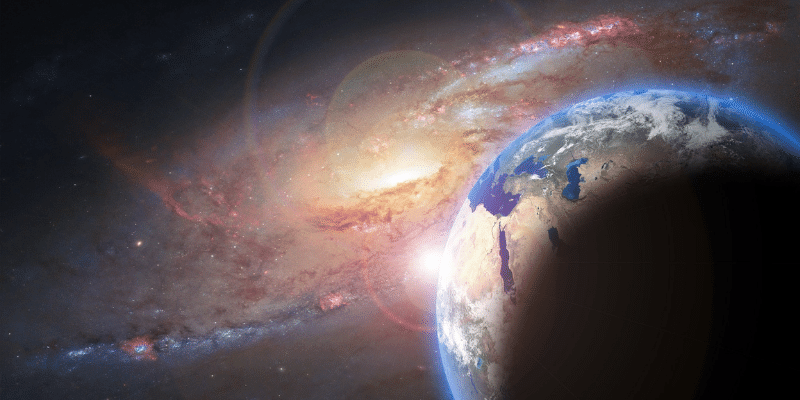
「氷河期」なんて映画の中の話でしょ!
なんて思っている読者様も、いらっしゃるかもしれませんね。
筆者も最初は、夏がこんなに暑いのに氷河期なんてありえないと思っていました。
でも「小氷河期が来る」という説には、ちゃんと科学的な根拠があるのです。
「2030年代に太陽の活動が60%低下し地球は小氷河期に入る」
この説は、英国・ノーザンブリアン大学の「ジャルコヴァ教授」が発表しました。
この章では「ジャルコヴァ教授」の研究について、分かりやすく紹介しましょう。
太陽の活動状態が変わる
「2030年代小氷河期が来る」
ジャルコヴァ教授の、ある発見から始まりました。
- 太陽内部には2つの異なる磁気波がある
- この2つは11年周期で変化する
ジャルコヴァ教授が発見した「2つの異なる磁気波」が変化する事によって、小氷河期が訪れるというのです。
そしてそれは「11年周期で変化」をしていて、2030年代が起こる時期とされています。
新たに発見された「2つの磁気波」を元に算定したところ
- 太陽の活動は6割も低下
- 黒点の数が著しく減少する
太陽の活動状態が、このように変わる事がわかったのです。
太陽の内部構造について詳しくは、こちらも是非読んでみてくださいね。
太陽の温度は実は平温⁉︎内部構造と26度説を詳しく解説します
マウンダー極小期が小氷河期の原因?
太陽の活動が低下する、というのはなんとなく想像ができると思います。
では、太陽の黒点の数が減少するとどうなるのでしょうか?
黒点の減少でマウンダー極小期になる
おおよそ1645年から1715年の太陽黒点数が著しく減少した期間の名称で、太陽天文学の研究者で黒点現象の消失について過去の記録を研究したエドワード・マウンダーの名前にちなむ。
引用:Wikipedia
黒点が減少することで起こる「マウンダー極小期」は、地球の寒冷期の原因とされています。
マウンダー極小期の地球への影響は?
中世における小氷期中頃の寒冷期の遠因と目され、この時期のヨーロッパ、北米大陸、その他の温帯地域において冬は著しい酷寒に震え、暦の上では夏至であっても夏らしさが訪れない年が続いた。北半球平均気温は極小期の前後と比べて0.1 – 0.2度低下したのではないかとされている[2]。
引用:Wikipedia
中世とは17世紀初頭ですが、温帯地域でも冬は極寒となり夏は涼しい気候となりました。
ジャルコヴァ教授は「太陽の黒点の数が著しく減少」することで
「2030年に太陽の活動状態が、マウンダー極小期になる」
と発表しています。
太陽はこれから、マウンダー極小期に突入するかもしれないのです。
それが「小氷河期」です。
2030年氷河期が来るとどうなるのか?
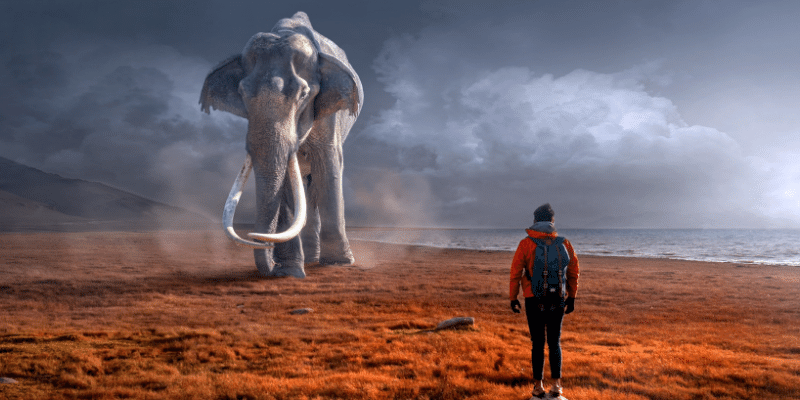
ジャルコヴァ教授は「小氷河期の到来」についてあくまで、断言はできないとしています。
しかし「97%の精度」で訪れる、との予測を立てています。
実際に小氷河期が来ると地球や日本はどうなってしまうのでしょうか?
400年前にもあった小氷河期
2030年はあと少しですが、400年前にも同じような状況がありました。
約400年前の寒冷期 = 日本は江戸時代
江戸時代の7大飢饉のうち最初の「寛永の大飢饉」が起こった頃の状況になる
どんな状況だったか想像できますか?
大飢饉で作物も実らずに、人々は食べるものにも困り餓死する人もたくさんいました。
また、小泉八雲が書いた『怪談』の中に「雪女」という話があります。
雪女とは
常に「死」を表す白装束を身にまとい男に冷たい息を吹きかけて凍死させたり、男の精を吸いつくして殺すところは共通しており、広く「雪の妖怪」として怖れられていた
引用:Wikipedia
小泉八雲の話は「武蔵の国」のことを書いています。
北の地方の雪国の話ではなく、現在の関東地域周辺の物語です。
この「雪女」は、冬の死を身近に感じさせる「雪の妖怪」として表現されています。
小氷河期が来ると「雪女」を怖れていた、江戸時代のようになるかもしれません。
- 外に出たら命が脅かされるほどの寒さ
- 従来の暖房が効かないほどの厳しい気温
極寒の生活に現れる「雪女=凍死」を考えただけでも、寒気がしますよね。
食糧危機が起こる
江戸時代は寒冷期の影響で気温が低く、冷夏による不作で何度も飢饉が起こっていました。
現在は「食糧生産量の増加」や「保存技術の発達」のため、食糧危機は身近に感じることはないでしょう。
しかし世界に目を向けると、人口の増加や発展途上国なども多く決して安心はできません。
厳冬や冷夏が続けば、食糧危機はあっという間に現実味を帯びてくるのです。
先進国の中では、とても低い水準です。
小氷河期によって世界的な食糧危機となった場合、食料品を輸入に頼る日本もひと事ではありません。
食料危機はあっという間に、日本中にも広がっていくでしょう。
野生動物による病気媒介・事故
小氷河期によって、植物が枯れてしまう事が予想されます。
餌の足りなくなった猪や鹿、熊などの野生動物が人間の生活圏に入ってきたらどうなるでしょうか?
人を襲う事故が増えたり、病気を媒介する可能性は十分に考えられます。
17世紀に、世界中で大流行した「ペスト」という感染症。
寒さによって餌の足りなくなったネズミが、人里に出てきたことが感染拡大の一因となったといわれています。
現代社会でペストが深刻な被害をもたらすというのは、少し考えにくいかもしれません。
しかしコロナが世界中で猛威を振るったように、何が起こるかは分からないのです。
海や川・湖の凍結によるエネルギー問題
小氷河期が起こると、海や川、湖が凍結することになります。
海が凍結すると起こること
北欧周辺など極地の海が凍ることにより、貿易等に影響が出る可能性があります。
船の航行が難しくなり、簡単に他国との貿易ができなくなります。
そのため石油などの輸出入も含め、供給が止まってしまいます。
石油の輸入が止まると、日本の産業やエネルギーはとても大きなダメージを受けます。
川や湖の凍結で起こること
東日本大震災以降、原子力発電の代わりとして他の方法でのエネルギー供給を模索しています。
そのひとつが、水力発電です。
日本国内のエネルギー・発電の供給量に占める、水力発電の割合は8%程度です。
しかし、日本国内の自然エネルギーの全発電電力量に占める割合は20.8%。
そう考えると、8%は決して少ない数字ではありません。
川や湖が凍ることにより水力発電が滞り、エネルギーが不足することも考えられます。
また湖や河川が凍結した場合は、水不足の心配があります。
水の確保を、考えなければなりません。
氷を溶かすためには、エネルギーが必要となります。
「エネルギーの不足」に伴って「水が不足」する可能性が出てくるのです。
日本だけではなく、世界でも水不足が深刻化するでしょう。
2030年氷河期が来るとどうなるのか?まとめ
最初は軽い気持ちで考えていた「小氷河期」。
まさかあるわけがないと思っていたのに、想像よりはるかに衝撃的な内容に筆者も驚きました。
もし本当に2030年に小氷河期が来たら・・・
- 食糧危機や水不足
- 野生動物による病気媒介・事故
- 海や川・湖の凍結によるエネルギー問題
このような問題が起こると、予想されます。
世界全体にとって非常に苦しい時期がやってくるかもしれません。
しかし、ジャルコヴァ教授は
「小氷河期が必ずしも到来するとは限らない」
ともいっています。
いずれにしても、2030年はそう遠い未来ではなくあと少しでやってきます。
何かが起こった時、簡単に世界は危機にさらされます。
その時のためにも今から心の準備をして、冷静な行動をしたいものです。
最後までお読みいただきありがとうございました!
スポンサーリンク

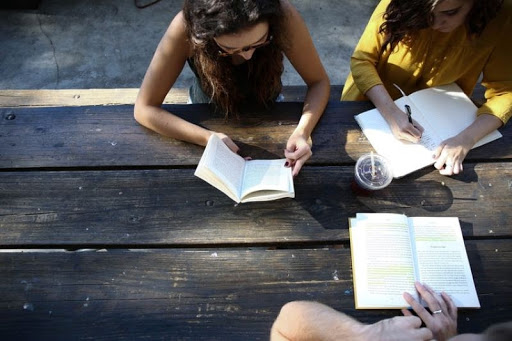



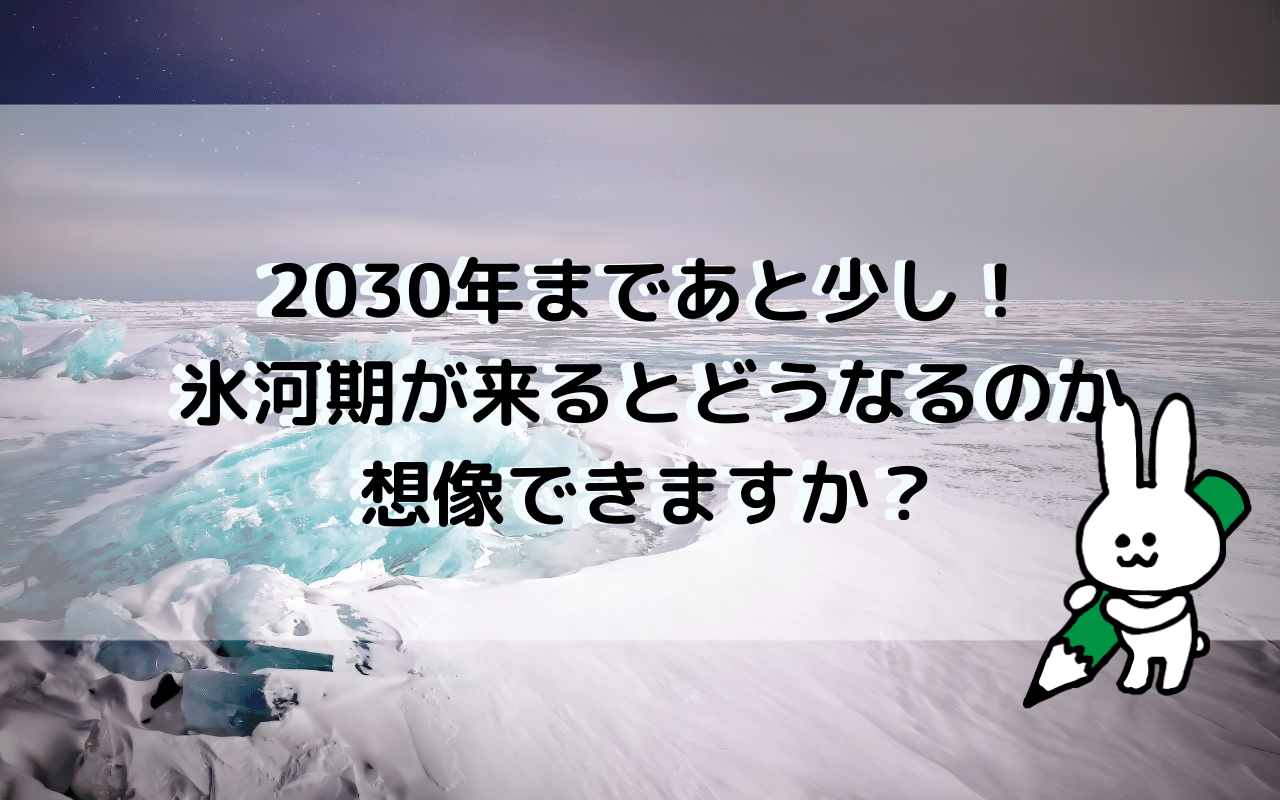
コメントはこちらからどうぞ